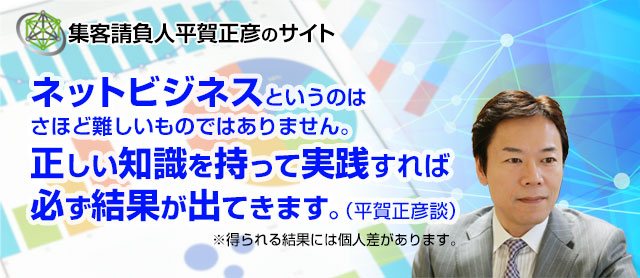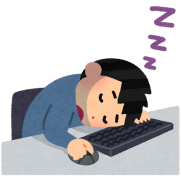公務員の職務と副業
公務員の副業が禁止される理由は、特定の企業との癒着を防ぐことが理由のひとつにあります。
談合事件などが時々ニュースになりますが、公共事業への入札・落札時などの公平性を保つためにも、当然といえば当然のことですね。
また、公務員に限らず、本業の職務に専念することは社会人としても当然のことです。
本業以外で忙しくて本業がおろそかになったり、アルバイト先でけがをしたり、過労から体調を崩して欠勤や入院したりとなると本末転倒です。
さらに、安定した職場にいながら副業をすることに対して、世間の厳しい目もあることも否定できないでしょう。
どんな仕事をする場合でも、まず、本業をきちんとやりきること、それを肝に銘じておくことが大切ですね。
確認!副業で確定申告が必要な場合
1年が経つのはほんとうに早いもので、今年も「確定申告」の時期がやってきました。
毎年、この時期になると書類作成に「深刻」に悩む人も少なくないと思いますが、深刻に悩むほど収入があるのは、ある意味贅沢なのかもしれませんね。
あっ、副業の場合、確定申告が必要になるのは「収入」ではなく「所得」が20万円を超えた場合ですので、その点を間違わないようにしてくださいね。
つまり「所得=収入−経費」になりますので、収入が20万円を超えても、それを得るための必要経費を差し引いた額が20万円までに抑えられるといいのです。
でも、ほんとうなら、そんなボーダーラインで悩むより、本業を超えるほどの大きな所得があれば、思い切って独立できるのですが……。
公務員の副業は、きちんと申請を
就業規則で副業禁止をうたっている企業は少なくありませんが、不況の時代を反映してか、それらを認める大手企業もあり、注目されています。
その背景には、本業以外で学んだことを仕事にフィードバックしてほしいという、経営側の期待もあるからです。
公務員は、副業が禁止されていることが知られていますが、農村地帯での兼業農家や、家がなんらかの店舗を経営している場合などは「手伝い」という形で認められます。
また、神主やお寺の住職が学校の先生や市役所に勤務するケースもめずらしくないですね。
このように、公務員が本業以外の仕事に関わることが許可されることもありますので、所属部署の上司に相談して、きちんと申請をするようにしましょう。
非常勤勤務の場合、副業は?
公務員の場合、所定の条件を満たし、しかるべき手続きをすれば副業が認められることもありますが、非常勤勤務の場合はどうなのでしょうか。
結論からいいますと、非常勤勤務の場合は正規の公務員ではありませんので、副業をすることに対して問題はありません。
このことは「職員の兼業の許可に関する政令」など法律によっても明確になっていますし、自治体独自で作成される「非常勤要綱」などでも、兼業禁止の規定はないようです。
しかし、非常勤勤務であっても、人目につくような目立つ職種と掛け持つことは自粛したほうがいいでしょう。
たとえば、市役所で働く場合、正規雇用かそうでないかは第三者からは分かりにくいため、誤解を招くこともあるからです。
公務員の副業と世間の風当たり
正規雇用の社員がサイドビジネスをするためには、いろいろとハードルがありますが、この不況の時代、サイドビジネスを推奨する企業も少なくありません。
その狙いは、サイドビジネスで知り得たノウハウを本業にフィードバックして、そこから得るものがあるからです。
ただし、公務員の副業は原則・禁止されていますし、所属部署に申請して認められた場合でも世間の風当たりがきつく、誤解を招くこともあります。
公務員の副業の目的は給与収入のカバーがありますが、高度経済成長時代と違い、ボーナスを含めると、むしろ一般企業よりも安定しているといえます。
現役時代は、定年退職後に備えて資格や免許を取得して「自分のひきだし」を増やしたほうが賢明かもしれませんね。
自分の職務をまっとうすることを考える
公務員の副業(サイドビジネス)に関しては、たとえ、休職中であっても毅然とした態度を取ることが求められます。
いろいろな不祥事が問題になっていますが、飲酒運転の検問に引っ掛かって、乳児を置いて逃げようとした育児休暇中の女性警察官がいることは、大変残念なことです。
このような不祥事を起こすと、会社勤めのサラリーマンや自営業に比べ、より厳しい社会の目にさらされるのが公職に就く宿命といっても過言ではありません。
公私混同はもちろん、たとえ休職中であっても、自分の置かれた立場を考えて行動をすることは大切だといえますね。
公務員で副業(サイドビジネス)を考えている人は、それよりも、自分の職務をまっとうすることを考えてもらいたいと思える典型的な事例です。
すべてが禁止の対象ではない
公務員の副業(サイドビジネス)に関しては、いろいろな意見がありますが、やはり、誤解を招くような行為はしないことが望まれます。
これは、人目につく場所で副収入を得る・得ないに関わらず、ちょっとでも後ろめたい気持ちがあるのなら、止めておくに限ります。
もちろん、すべての職種を禁じられているわけではありません。
たとえば、地方都市の市役所職員の家が農家という例はいくらでもありますし、そこに勤務する人が、休日を利用して農作業をすることはけっして珍しいことではありませんね。
また、神主や僧侶が学校の先生をしている例もよく見掛けますね。
このように、公務員の副業(サイドビジネス)はすべてが禁止の対象ではないことも、改めて確認しておきたいと思います。
万全の対策を取って臨むことが大切
公務員の副業(サイドビジネス)は、原則として禁止されていますので、誤解を招かないためにも、事前に所属する部署の上司と相談することをお勧めします。
たとえば、自分の専門知識を活かして講演活動をしている人も少なくありませんが、そのとき、報酬の扱いなどが問題になる可能性もあります。
なかには、まったくのボランティアでの活動をしている人もいますが、とにかく、問題を透明化させておきたいものです。
人前に出る機会が多い事例として、プロスポーツ選手の場合が考えられますが、ある女子プロ選手は、試合で得た報酬は受け取らないことを公言しています。
この事例からも、公務員が副業(サイドビジネス)とみなされる行為をするときは、万全の対策を取って臨むことが大切だといえます。
本業に専念して、スキルアップすることも
公務員の待遇については、触法行為がない限り「解雇」にならないという認識があり、一般的にも広く知られていることです。
そのしくみにメスを入れる法案がメディアでも取り上げられましたが、その自治体のトップが入れ替わったことによる今後の進展が注目されます。
公務員の副業について、身近な例としては、実家が農業を営んでいる場合、休日に田んぼ仕事をしている姿はよく見かけることです。
また、住職や神主と兼業しているケースもありますので、みんなが認める公務員の副業はたしかに存在します。
しかし、あきらかに違法だと思われるケースや、誤解を招く恐れがある場合は、本業に専念して、住民サービス向上のためにスキルアップすることを優先してください。
公務員の家族は?
こんなことをいうと、公務員は定年退職後まで恵まれた環境にあると、世間の風当たりがますます強くなりますね。
いまのご時勢ですから、普通に勤務している限り解雇の心配もありませんし、退職金は一般企業よりもはるかに多い?
公務員は待遇が良過ぎる、そう思われても仕方ないかもしれません。
その代わり、私の家では父が公務員ですが、それを支える母の苦労は相当なものだと思います。
なにしろ、世間の目が厳しいですから、父が公務員というだけで、母や兄の私生活まで監視されているみたいです。
もちろん、私に対しても……。
ですから、家族が副業ひとつ選ぶにも神経を使わなければなりません。
家族でも、人目につくところで副業をすることも難しいのです。
定年後の公務員は?
公務員を父に持つ娘です。
以前、定年退職後の公務員の仕事について少し触れたことがありますが、今回はそれについてお話したいと思います。
公務員は、「守秘義務」の関係もあり、原則として副業禁止になっています。
また、公務員は、なんらかの不祥事を起こさない限りは解雇にはなりませんので、「雇用保険」もないのです。
公務員といっても職種はいろいろですが、代表的なのは地元の役所に勤める人で、私の父もそのひとりです。
それらの人が定年退職した後は、地元のなんらかの団体に嘱託として雇用されることが多いそうです。
これは公務員の友人から聞いた話ですが、定年退職した公務員を嘱託として迎えるのは、一般企業でいう雇用保険の代わりになるそうです。
公務員と講演活動
メディアに登場する人のなかには、医師や弁護士の本職をもっている人も多くあり、そのなかには明らかに公務員だといえる人もいます。
公務員の副業は、「国家公務員法」や「地方公務員法」によって原則禁止されています。
しかし、農業や商店などの家業はもちろん、講演活動や執筆活動などについては、職場に届けることによって許されているケースが多々あります。
教育や健康、福祉に関するイベントが各地で行なわれますが、そのときに、公務員の職にある人を講師として講演会を開催することもあります。
そのときの報酬の有無や金額などは個々によって違いますが、公務員がこういった講演活動をすることは、副業収入以上に得られる貴重なものがあると思われます。
公務員と早期退職
副業を容認あるいは推奨する企業が増えてきましたが、公務員の副業に関しては、依然、厳しいものがあるといえるでしょう。
もちろん、これまでお話したように、正規の届出をすれば認められる場合もありますが、民間企業と同じというわけにはいきませんね。
そんななか、子どもが学校を卒業して手が離れたなど人生の節目をきっかけに、早期退職を選ぶ公務員も増えてきました。
それと同時に自分自身の「第二の人生」もスタートします。
テレビ番組でも、早期退職後に田舎暮らしを始める公務員の姿がよく取り上げられています。
公務員が副業をする場合は、現役時代ではなく、退職して一段落してから取り組めるように、準備しておくのもひとつの方法だと思います。
公務員と地域活動
60歳定年が一般的になっていますが、その後も「嘱託」として残る人や、すぐに再就職をする人も増えてきています。
その背景には、結婚年齢の高齢化に伴い、子どもの教育費がまだまだ必要だということもあります。
定年後の再就職先には、前職とはまったく畑違いのところを選ぶ人もいますが、永年培った経験を活かした仕事に就く人も少なくありません。
公務員の副業は現役時代には難しい点がありますが、定年退職後には、それまでの仕事を活かした仕事や、在宅での副業をすることも可能です。
もちろん、再就職は「天下り」ではなく、正規の方法で採用されることが前提です。
また、地域活動に貢献できることも、地元に密着した公務員の経験を活かす方法ですね。
公務員の副業と確定申告 その(1)
サラリーマンなどの副収入所得が年間20万円を超えた場合、職場での「年末調整」とは別に「確定申告」をする必要があります。
この場合、「所得」は「収入−必要経費」ですので、きちんと帳簿をつけて金銭管理をしておくことをお勧めします。
また、確定申告の対象期間は前年1月1日から12月31日ですので、併せて覚えておきたいですね。
公務員の副業は原則禁止ですから「当然、確定申告の必要はない」と思われがちです。
しかし、医療費控除を受けたい場合は、公務員の副業の有無関係なしに自主的に確定申告する必要があります。
ですから、扶養家族に掛かった医療費の合計額から生命保険でカバーできる分などを差し引いて、10万円を超えた場合は確定申告することをお勧めします。
公務員の副業と確定申告 その(2)
「確定申告」は、毎年2月16日〜3月15日に行われ、その対象になるのは前年の1年間です。
公務員の副業が原則禁止ということは、内外ともに認めていることですが、公務員の副業禁止とは別に、確定申告が必要な場合もあります。
給与所得者が確定申告を必要とするときといえば、副収入所得が年間20万円を超えたケースが考えられます。
そのほか、生命保険の満期保険金を受け取った場合など、本業以外でなんらかの収入があった場合も確定申告が必要になります。
医療費控除は「自主申告」ですので、忘れていてもペナルティーはありません。
しかし、確定申告の対象でありながら申告しない場合は、重加算税、無申告加算税、過少申告加算税などの対象にもなりますので要注意です。
公務員と確定申告
深刻な不況の影響もあり、副業を認める企業も増えてきましたが、公務員の副業に関しては依然としてきびしいものがあります。
公務員の場合でも副業を認められる場合があり、所属の上司を通じて正規の手続きをすれば可能になるのです。
それとは別に、公務員の「確定申告」に関してネット上で質疑応答があり、大変興味をもちました。
質問の内容を要約すると、「自分は公務員だけど医療費控除が受けられるのか」というものです。
それに対する回答は、「医療費控除は公務員である・なしに関係なく、確定申告すれば受けられる」という主旨でした。
つまり、公務員の場合も会社員と同じで、個々のケースによりますが、確定申告をすれば所得税が還付される可能性もあるのです。