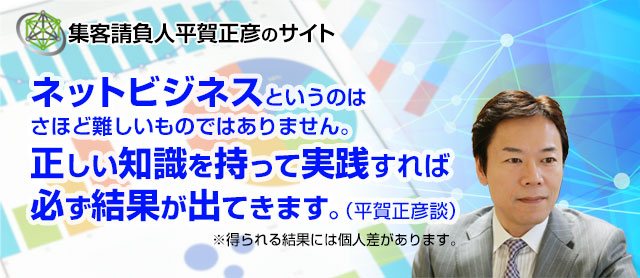公務員が副業をはじめるとき
在宅でできるネット副業が、サラリーマン・OL・主婦・学生など、老若男女問わずに人気です。
激動の時代ですので、在宅ネット副業で少しでも貯えをつくっておきたい、というのは、誰もが考える生活の知恵だともいえます。
その一方、世間的には安定している、と言われる公務員の人でも、在宅ネット副業をはじめようとする動きがあります。
まだ一部ではありますが、公務員であってもどうなるか分からないときのために、在宅副業で副収入を、という考えがあるのは当然のことです。
また、公務員が在宅副業を考えるのは、もう一つの理由があり、それは転職のためです。
転職活動を考える人が、活動中の資金のために在宅副業をするわけです。
在宅副業を考える理由はまさに人それぞれ、といって良いでしょう。
公務員の副業はワガママ?
公務員が副業をしたい、などと言えば、周囲のいわゆる”市民”は猛反対するでしょう。「公務員は安定しているのだから、副業なんてもってのほか!」などと言うかもしれません。
ですが、公務員とてさまざまで、世間がいうような高給取りばかりではありませんよね。
手取りに心細さがあり、副業を欲している公務員も大勢います。
そのいっぽうで、公務員=公僕なのだから、副業などしてはいけない。そんな職業ポリシーを抱える公務員も多いでしょう。しかし、それは結局、周囲の声にこたえただけの結果であることも多いものです。
もしあなたが公務員であるなら、今一度、自分に問いなおしてみてください。
公務員は、ほんとうに副業を必要としていませんか?
公務員の副 ボランティア活動はどうなるの
自分の所属する部署に届出をしない限り、認められない公務員の副業ですが、定年後の人生に備えて「自分磨き」をすることは可能です。
たとえば、正規の休暇を利用して、地域行事に参加したり趣味の講座に参加することは、自分の知識を高めるだけでなく、新たな友人づくりのきっかけにもなります。
そこで、問題となるのは、自分が勤める部署の勤務時間中にボランティア活動をすることです。
この場合は、ボランティアの内容にもよりますが、所属部署の上司とも事前に相談してから参加することをお勧めします。
公務員の副業にはいろいろな問題がかかわってきますが、万一、事故が起きたとき、包み隠さず状況報告ができるためにも、段階を踏んでから行動することをお勧めします。
お金に換えられないものを見出す努力も必要な時代
公務員は副業(サイドビジネス)について議論する以前に、勤務体制や官僚の体質そのものにメスを入れる動きもみられる時代です。
高度成長期には人気が高かった民間企業への就職ですが、1973年のオイルショック以降、安定志向を目指す傾向へと社会の流れも大きく変わりました。
そのため、公務員の副業(サイドビジネス)以前に、職員としての資質も問われるようになり、早期退職を選ぶ人も増える傾向にあります。
もちろん、子育てや住宅ローン返済などが一段落ついたため、第二の人生を楽しみたいという人が含まれているのは、いうまでもありません。
長い人生をより価値的に生きるためには、副収入を得ることだけでなく、お金に換えられないものを見出す努力も必要な時代かもしれません。
公務員への風当たり
ネットを検索していると、公務員の副業に関して、いろいろと興味のある質疑応答があります。
また、ある法律関係のテレビ番組では、公務員が出店しているフリーマーケットが副業にあたるかどうかについて、議論が展開されたこともあります。
番組に出演していた4人の弁護士の見解はわかれましたので、実際、裁判などになるとどういう展開になるかは予想できません。
しかし、それとは別に、公務員の副業に関する世間の風当たりが半端ではないという空気がありました。
臨時職員待遇の人でも、市役所などに勤める場合は、目立つ場所での副業自粛をうながされているのが現状です。
そういう背景もあり、副業に関しては必要以上に神経質にならざるを得ないのです。
公務員の副業 「無届兼業」が懲戒処分対象になった例も
公務員の副業(サイドビジネス)に関しては、民間企業に勤務するサラリーマン以上に厳しいものがあります。
もちろん、公務員の副業(サイドビジネス)といっても、所定の手続きさえ済ませておけば許可されるものも少なくありません。
たとえば、実家が農業やお店、神社やお寺の場合などは、みなさんもよくご存知の例です。
本業以外で副収入を得ることに対しては、社会全体として厳しさを増しているなか、その反対に、本業へのフィードバックを期待して推奨する企業もでてきています。
しかし、あくまでも本業に支障をきたさないことを大前提としています。
最近では、「無届兼業」のブログ・アフィリエイト収入が懲戒処分対象になり、依願退職に至った警察官の事例もあります。
本業の勤務時間中の私用は許されるものではない
ただでさえ世間の目が厳しい時代にあって、公務員の副業(サイドビジネス)については、辛口評価をされるのが当然、といっても過言ではないでしょう。
人間は感情の動物ですから、現時点ではリストラや解雇がない立場にいる公務員が副業(サイドビジネス)をするのは「とんでもない」という風潮があります。
ましてや、本業の勤務時間中に私用をするなど、許されるものではないことを肝に銘じておきたいですね。
消防署は緊急出動が要請される部署ですが、勤務時間中に、制服姿のまま病院の診察を受けた消防署職員があり、ニュースでも取り上げられました。
この場合、上司の許可を得たうえで、消防車両を使って病院へ行き、同僚は駐車場で待機していたというのですから、公私混同もいいところですね。
公務員の副業 兼業に関するある事例
公務員の副業については、自分が所属する部署の長が許可した場合のみ認められることになっています。
また、仕事と特別な利害関係がないことや、本来の職務遂行に支障がない場合という条件も加わりますので、一般企業よりも厳しいといえますね。
つい最近、40歳代のある男性職員に、プロスポーツの審判員を14年の長きに渡りつとめていた疑いが浮上しました。
試合の報酬を一切受け取らないプロ選手はいましたが、前述のケースでは、兼業許可申請書が未提出のうえに、報酬を受け取っていたことが問題になるということです。
一般企業に勤めるプロスポーツ選手は、報酬を受け取ることに問題がありませんが、公務員の副業は、同じようなケースでも難しいといえる典型的な事例ですね。
自分の職務をまっとうすることを最優先
公務員の副業について厳しくいわれるのは、雇用面全般において安定した環境にあることに対する世間の目が関係すると思われます。
特に、地域に密着した官公庁に勤める場合、なんらかの形で副収入を得ているとすぐに発覚しますが、兼業に関してはそれだけ厳しい時代になったといえますね。
外でアルバイトをすることはもちろんのこと、たとえば学校に勤める音楽教師が自宅でピアノ教室を開いて報酬を得ることもできなくなっています。
ただし、私立学校で教鞭を取っている場合は、その学校の方針にもよりますが、公務員の副業ほどは厳しくないと思われます。
いずれにしても、公的立場にあり税金から給料をもらっている人は、自分の職務をまっとうすることを最優先することが大切です。
「明らかに違法な職種は避ける」との強い信念を貫くこと
公務員の副業についてはいろいろと制約がありますが、株やFXなど自己資金を使った投資や、所有する不動産での収入は認められています。
また、家が農業や商店を経営している場合もよくあるケースですし、お寺の住職や神社の神主が教職に就くケースもありますね。
それと、文筆業や講演会での仕事も事前に許可をもらえれば可能ですが、賃金などの規定がありますので、それに従うことが大切です。
変わったところでは、市役所勤務のプロスポーツ選手の例もありますが、その場合、試合で得た収入は受け取らないことを公言していました。
このように、公務員の副業については例外もありますが、「明らかに違法な職種は避ける」という、強い信念を貫くことが大切です。
本業と副業との捉え方
公務員の副業は、原則として禁止されていますが、家が神社やお寺などの場合は、そこの神主や住職をすることが許されているのは、一般的に知られていることですね。
たとえば、市役所勤務の職員や学校の教職員の例がありますが、身近にも、そのような人がいるのではと思われます。
これらの場合、別の角度から捉えると、代々続く家業の神主や住職のほうを「本業」とすることもできます。
本業と副業との関係については、あくまでも、その人の位置づけによって決めるもので、収入の割合で第三者が判断できるものではないからです。
それとは別に、公務員の副業として農業がありますが、これも、兼業農家の場合は、休日を利用して農作業をすることはごく自然な形になりますね。
事前に所属部署の上司に相談して許可をもらう
公務員の副業は、原則・禁止されていますが、専門分野に関する講演活動などは認められるケースもあります。
地域主催のセミナーの講師の経歴をみると、明らかに公的機関に勤務している人だとわかるような人もいますので、けっして珍しい存在ではないと思われます。
また、福祉や医療関係など、実際にその分野にいる人でないとできない講義もありますので、このような形での公務員の副業は増えてくる可能性はあります。
そのとき、問題になるのは、講演料をどうするかですが、実際、どのような形になるのかは、個々のケースによると思われます。
しかし、あらぬ誤解を招かないためにも、公職にある人がこのような活動をするときは、事前に所属部署の上司に相談して許可をもらうことをお勧めします。
副業を始める前に必要なこと
在宅副業だから、本業の勤務先にはばれないだろうと許可なしに副業をはじめている人もすくなくありません。
しかし、副業をはじめる前に本業となる勤務先に許可をもらうことが大切です。
あらかじめ勤務先に許可を貰っておけばマイナンバー制度の導入により、勤務先に副業がバレてしまうのではないかと心配する必要もないのです。
あとあとトラブルになることがないように、所属部署を通して副業の届け出をしましょう。
副業をはじめたことで本業の妨げになるようなことがないよう、自覚をもつことが大切です。
また、在宅副業であっても、本業の職種と利害関係のある副業は避ける必要があります。
公務員の副業は原則として法律で禁止されています。
しかし副業が絶対に禁止というわけではありません。個々の事情により許可をもれえることもあります。
大切なことは本業をおろそかにしないこと
サラリーマンの副業(サイドビジネス)には、いろいろな働き方がありますが、大切なことは本業をおろそかにしないことです。
この不況の時代にあって、サラリーマンに副業(サイドビジネス)を推奨する企業もありますが、本業へのフィードバックを期待しての部分もあります。
また、公務員など、本業以外で収入を得ることになんらかの制限がある職業の人は、事前に届け出をするなど、しかるべき対策をすることが必要なことはいうまでもありません。
ブログを使ったアフィリエイトは身近な存在ですが、公務員としてのあり方が問われた事件も記憶に新しいことです。
とにかく、どんなことをするにも、絶対にバレないことはありえないことだと、肝に銘じておくことをお勧めします。
仕事を続ける妻の事例から
「公務員の副業」に関して、この記事のためのネタといっても過言ではない、大変興味深い話があります。
あるテレビ番組で、「人気のスポーツ選手を支えた妻の特集」をやっていましたが、そのなかで、プロ選手である夫を支えながらも自ら仕事を続けている事例がありました。
11歳年下の夫は、単身赴任。妻が同居をしないで仕事を続ける理由のひとつとして、彼女が公務員であることが関係しているかもしれません。
プロ選手は体が資本の世界ですから、こども2人を抱えながらも仕事を続けている妻の心情も十分理解できます。
しかし、妻が他の職種だったら、夫と同居して仕事を続ける選択肢もあったのではと思います。
「公務員の副業」以前に、やっぱり公務員は安定した仕事だと、改めて考えさせられた事例です。
公務員の副業に対する世間の批判
公務員の副業だけでなく「○○組合」など、勤務先によっては副業を禁止しているところがあります。
このような規則があるのは、勤務先団体の地域での役割が大きいことが考えられます。
また、そのような団体では、明らかに自分の過失による重大な事故を起したときは、そこにいられなくなるような雰囲気もあると聞きます。
そのような話を耳にしたのは、もう何十年も前のことですから、いろいろな面で世間の目が厳しい現代にあっては、さらに厳しいものがあるといえるでしょう。
なんらかの事件・事故の報道のたびに職業まで公表するのには賛成しかねますが、そんなとき公務員との報道があると、一気に批判ムードが高まる感じがします。
ましてや、公務員の副業に対する世間の批判は、相当なものであると思われます。