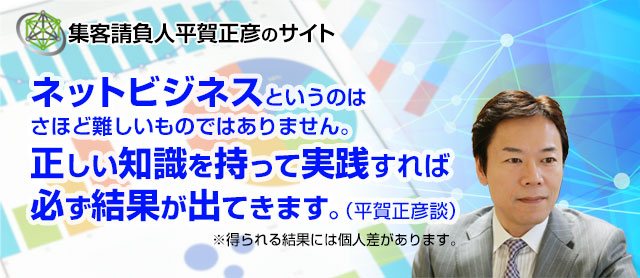法人向けビジネスと消費増税の関係
先日のニュースで、アマゾンが2023年6月30日にKindleストアを廃止するという報道がありました。
ちなみに、通販事業自体は2019年に撤退しています。
当時のマーケットシェアは、アリババの50%超に対してアマゾンは0.7%に過ぎなかったとか。
日本や北米ではマーケットシェアが50%を超えているらしいので、0.7%という数字は低すぎて驚きましたね。
しかし、中国人セラーが北米やヨーロッパ、日本などのアマゾンマーケットプレイスに出品することができる、グローバルセリングは十分な利益が出ていて現在も継続されています(※中国国内に本社がある出品者に限る)。
ところで、皆さんもすでにお気づきだと思いますが、最近、アマゾンで変な日本語を使って販売している販売者が増えてきましたよね。
おそらく、今後も更に増えると思われます。
レビューも変な日本語だったりするので、レビューを書き込む部隊なども存在するのでしょう。
もちろん、良い商品であれば全く問題ありませんが、私は何度か後悔させられたことがあります(苦笑)。
法人向けのビジネスは手堅い
さて、現在コロナ禍で消費が落ち込んでいますが、コロナ以外で消費が落ち込みやすのが増税です。
その落ち込みをいかに軽くするのかという観点でお話いたしますと、法人向けのビジネスは手堅いと思います。
エンドユーザー向けのビジネスに比べて落ち込みが少ない、もしくは増税前とほとんど変わらないということもあります。
なぜなら、日本の税制が法人税を下げて、所得税や消費税を高くしようという流れになっているからです。
税金を法人から取るのか、個人から取るのかということですね。
つねづね経団連が消費増税に賛成しているというのは、この辺に理由があるのかもしれません。
法人税の現在に関しては世界的にそういった方向ですね。
アメリカでは、トランプ前大統領が公約であった、法人税を筆頭とした大規模な減税と規制緩和をすることで景気が良くなったことがありました。
ちなみに、主要国の中では保護主義を強めているアメリカとイギリスのみ労働者の平均賃金が3%以上上がっているのだとか。
というわけで、法人税が安くなる方向に向かっているということは法人の体力は引き続き維持されることになるわけですね。
法人向けビジネスで大きく業績を上げた事例
私の会員さんではご自身のビジネスを法人向けにすることで大きく業績を上げた事例がいくつもあります。
その中から代表的な事例を2つご紹介いたしましょう。
出張整体を行っている岡林さんは、従来個人向けに行っていたサービスを法人向けにすることで大口顧客を獲得しました。
今では一般的になってきた企業向けの整体サービスですが、岡林さんは10年近く前からやっていましたから第一人者だと言えます。
次に、工具や人体模型を法人向けに販売している熊野さん。
彼の場合はもともと法人向けの商品を探していて上記のような商品を取り扱うようになったので、先見性があったということですね。
もちろん、上記のような商品だけではなく、エンドユーザー向けに教育教材とか健康食品なども扱って事業の多角化を進めています。
これらの成功事例を見ていくと、最初はエンドユーザー向けに行っていたビジネスを途中から法人向けにアレンジしたことがわかります。
一度の取引量が多いということと、リピート性が見込めるというのが大きなポイントですね。
法人向けのビジネスは集客コストが安い
以上のように、法人向けビジネスというのは時代の流れにもマッチしていると思います。
また、法人向けのビジネスというのは集客コストが安いというメリットがあります。
PPC広告などを出してみるとよくわかりますが、エンドユーザー向けのキーワードに比べると単価が安いことが多いですね。
そして、法人をターゲットにするとファックス番号とか住所を簡単に知ることができます。
つまり、ファックスDMを送ったり郵送DMを送ったりすることが簡単にできるわけです。
個人情報保護の関係でエンドユーザー向けのビジネスでは上記のようなことができない状況ですが、法人向けなら問題ありません。
会社で使っているファックスや郵便ポストというのは、ネットが普及する前に比べると使われていないことが多いです。
以前は毎日のように届いていたファックスDMが今では月に1〜2枚ということもあります。
そして、以前は束のように届いていた郵送DMが今では数えられるくらい少ないわけですね。
このブログをお読みになっている皆さんも、現在はエンドユーザー向けにビジネスを行っているかもしれません。
しかし、今のビジネスを法人向けにできるかどうかを考えてみても良いと思います。
たったそれだけのことで、将来への見通しが随分と変わってくることでしょう。